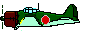
この物語はJU87氏がBBS-Qにおいて発表したものの転載です
PART-1
序
比較
弱点
零戦の種類
補足
20mm機銃
好敵手1
好敵手2
最終回
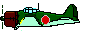
この物語はJU87氏がBBS-Qにおいて発表したものの転載です
PART-1
序
比較
弱点
零戦の種類
補足
20mm機銃
好敵手1
好敵手2
最終回
なんといっても日本の代表選手といえば、やっぱゼロ戦ですよね。 正式には 「零式艦上戦闘機」って名称だから、レイ戦というべきだけれど・・・ ドイツメッサーシュミットBf109、アメリカのPー51ムスタング、イギリスの スーパーマリン・スピットファイアと並ぶ世界の傑作戦闘機と称してよいでしょう。 どの個体が最強であるか?という比較はナンセンスでしょう。 実戦参加した時期も違うし、おのおのいろんな仕様の機体があります。 例えば零戦 21型(A6M2b)と52型(A6M5)とではまったく違う性質の機体といっても いいくらいです。Bf109だったらB型とF型というようにね。 しかも零戦が艦載機である というハンデを背負っているにもかかわらず 陸上基地で運用された彼らと肩をならべている!というのが、最大のポイントです。 とにもかくにもこの零戦が 「日本人の本質的なこころを表現した飛行機である」 という意味で非常に興味があり、また存在感のある機体である訳です。 この零戦の設計主任であった堀越氏は、この機体について 「12試艦戦(零戦の試作名称)の要求の一つ一つの項目は、航続力と空戦性能を 除けば外国の新鋭戦闘機と比べ最高の水準であったが、特別高いものではない。 しかしその項目の全てを一身に兼ね備える戦闘機を、実際に創り出すとなると これは容易ならぬ要求であった。いわば十種競技の選手に対して、その種目の 一部に単一競技としてのレコードを、大部分の種目に単一競技のレコードと同等か、 叉は極めて近いレコードを要求したもので、もし実現したならば世界の驚異であった」 と著書「零戦の遺産」の中で述べられています。 この不可能を可能にしてしまった零戦について 次回に続きます。
零戦って いったいどんな飛行機なんでしょうか? まずは単純にカタログデータの比較を、見てみましょう。 次の表は 同時期の各国のライバル達のデーターを、抜粋したものです。 時期 型式名称 全長 全幅 重量 馬力 速度 距離 武装 ------------------------------------------------------------------------ 1940 A6M2b 零戦21型 9.06 12.00 2410 940 533 3502 2Ox2 7.7x2 1941 キ-43-1 隼1型 8.83 11.43 2043 990 491 1146 12.7x2 ------------------------------------------------------------------------ 1940 F4Fワイルドキャット 8.76 11.58 3359 1200 512 1465 7.62x6 1942 F4Uコルセア 10.26 14.29 5556 2100 718 1609 12.7x6 5inロケットx8 1939 P38ライトニング 11.53 15.85 9806 1425 666 3025 20x1 12.7x4 1939 P40ウォーホーク 9.67 11.37 3607 1150 570 563 12.7x6 1941 P47サンダーボルト 10.92 12.43 6623 2300 764 764 12.7x8 5inロケットx10 1941 P51ムスタング 9.82 11.27 4581 1490 703 1529 12.7x6 ------------------------------------------------------------------------ 1937 Bf109E 8.74 9.86 2770 1200 578 1090 20x1 7.92x2 1941 Fw190A 9.00 10.50 4460 1700 640 1450 20x2 13x2 ------------------------------------------------------------------------ 1937 ハリケーン 9.82 12.19 3311 1280 550 1585 7.7x12 1938 スピットファイア 9.12 11.22 4663 1440 598 750 20x2 7.7x4 ------------------------------------------------------------------------ どうでしょうか? 一目瞭然ですね。 要約すると速度、上昇力、旋回性、航続力、離着陸性能及び火力を高い水準で バランスさせた万能戦闘機である となります。 しかもその発動機は940馬力(栄12型)と 列強国のそれと比較すると、明らかに 非力であるにも関わらずですよ。 速度や火力を重視すれば大きな馬力と機体が、運動性や航続力を重視すれば 小さな馬力と機体が必要というように、相反する問題を解決した ってのが スゴイ!といえませんか? なおかつ とても軽いんです。 超強力アルミニュウム合金ESD部材と、昇降舵操縦系統の改善によって その 操縦性能と空戦性能が、従来のそれと比較して格段の進歩を遂げたのです。 つまり 非常に乗りやすい飛行機だったのです。 が しかしこの傑作戦闘機にも、弱点があった!
堀越氏の零戦の遺産という著書からの抜粋です。 <設計者がみた弱点> 本機は1000馬力級戦闘機のチャンピオンであった。1200ー1300馬力級を含めて タイトルを取れたと思うが、1500馬力級の後の戦闘機と比べたら本機の弱点は 次にある。 1.馬力の過小 零戦の性能向上改造を阻んだ原因は、始めに小さい発動機を選んだことと換装 の為の設計技術者不足である。金星を始めから選べば、九六式艦戦より50%も 大きい飛行機になり、当時のパイロットからは到底受け入れられない機体だった。 2.急降下速度の不足 僅か1000馬力の発動機では、急降下制限速度を断然上げるのに、思う存分重量 をかけるわけにはいかない。艦戦の生命である軽快性を捨てない限り、急降下 速度を大して上げることは、物理的に不可能なのである。 3.高々度性能の不足 1000馬力級で中型空母から発進するためには、全開高度の低い発動機が必要で だった。日本では2速加給器が採用されて以来、高空馬力が額面値を割る傾向が あり、発動機の性能が向上されればされる程、その傾向が強かった。 4.高速時補助翼重く効き不足 日本の戦闘機が高速時に補助翼が重く、効きが鈍くなるのは空戦のテクニックに起因 する。すなわち空戦において日本機は、縦の面内の運動を重視する設計されて いた。その結果として高速時にかの症状が出てしまった。 5.防弾の欠除 防弾の欠除は日本軍用機の共通した短所であった。 1000馬力の発動機から、性能の一滴でも余計に引き出せという国家の至上命令 を任務に設計された零戦に、要求のない防弾まで行なう余裕が無かった。 対等の敵との戦いならば、防弾欠除も戦闘機としてはそれ程深刻な弱点には ならない と考えられていた。 さすがに設計者の言葉です。 大戦後期になると、米国機は特に2.3.5.の弱点をついて攻撃してきたようです。 すなわち 攻撃も退避も、高々度空域と急降下を利用する戦法です。 さて 次回は零戦の変遷についての話をば。
A6M1 12試艦戦 S14 2機 振動対策で2枚プロペラから3枚へ他小改修。 A6M2a 11型 S15 64機 A6M1の性能向上型。零式艦上戦闘機と制式採用さる。 A6M2b 21型 S15 3696機 初期量産型でゼロファイター伝説を築いた型。 航空母艦収納用に翼端を50cm折り畳み式にした。 A6M3 32型 S17 343機 換装及び翼端を50cmずつ切断し角形に整形した。 A6M3 22型 S18 560機 航続距離向上型。主翼をふたたび21型に戻した。 A6M3a 22型甲 S19 22型の20mm機銃改装型。 A6M4 32型に排気タービン式加給器付きの高高度実験機。 A6M5 52型 S18 2077機 後期量産型 推進式単排気管採用。 翼端は丸形の まま主翼を再び全幅11mに短縮。 A6M5a 52型甲 S19 521機 20mm機銃換装型。 A6M5b 52型乙 S19 風防前面に防弾ガラス装備 武装強化型。 A6M5c 52型丙 風防後部に防弾設備 武装強化型。 A6M6c 53型丙 S19 試作1機 水メタノール噴射装置付きに換装した。 A6M7 63型 S20 52型丙に爆弾投下装置を追加した、戦闘爆撃機型。 A6M8c 54型丙 試作2機 52型丙の換装による性能向上を狙った型。 この型の量産型を64型とした。 型式 発動機 馬力 全幅 速度 距離 武装 -------------------------------------------------------------------- A6M1 端星13 780 12.0固定 491 ---- 7.7x2 20x2 60kgx2 A6M2a(11) 栄12 940 〃 533 1891 〃 A6M2b(21) 〃 〃 12.0折畳 533 3502 〃 A6M3 (32) 栄21 1130 11.0固定 544 2378 〃 A6M3 (22) 〃 〃 12.0折畳 541 3333 〃 A6M5 (52) 〃 〃 11.0固定 585 1920 〃 A6M6c(53) 栄31 950 〃 --- ---- ---- A6M7 (63) 栄21 1130 〃 542 1519 13x3 20x2 250-500kgx1 A6M8c(64) 金星62 1500 〃 572 1500 13x2 20x2 500kgx1 いかがでしょうか? カタログデータは別として、操縦性能が優れているといえば21型らしいです。 大戦末期のある南方の部隊でのエピソードがあります。 この部隊は21型と52型の混成だったんですが、ベテランパイロットには52型が 操縦しやすい21型に経験の浅いパイロットが、それぞれ配されたそうです。 その戦果は ナント21型の方が優秀だったとか・・・
先の一覧表の中に A6M4ってのがあったけど、お気づきかなぁ? 気づいた人はとってもエライ! 実は以前から疑問だったんですヨ。 A6M3があって 番号が飛んでA6M5でしょう? A6M4は 無かったのだろうカ?ってね。 で 調べたけど不明だったんですなぁ。 そしたら たまたま古本で入手した 雑誌「丸」の別冊付録 日本の戦闘機 ってのに、記載されていた! その詳細は 零戦32型の1機に石川島製の、排気タービン式加給器を装備した高高度実験機。 空技廠で実験が行われ、三菱には直接関係の無い改造であったそうです。 この型をA6M4と読んだが、一般には発表されなかったそうです。 うーん これでまた一歩 完集に近づいた カモシレナイ・・・
零戦というよりも海軍戦闘機の主力機銃は、99式20mm固定機銃という名称です。 P氏のご指摘のように、スイスのエリコン20mm機銃を国産化したもので、別名恵式機銃 ともいわれていました。 製造権を購入して国産化したものですから、ライセンス生産になるんでしょうか? 似たような例として、ドイツの名エンジンDB-601を国産化したハ40などがありますネ。 で この99式20mm機銃は銃身の短い1号と、銃身の長い2号に大別されます。 さらにおのおのバリエーションが存在します。 1号銃(エリコンFF型の国産型) 1型 輸入したスイス製 零戦11型、21型 2型 1型をそのまま国産化した型 32型、22型 3型 2型を空気装填油圧発射式にした型 紫電11型 4型 弾倉式からベルト給弾式に変更 雷電 2号銃(エリコンFFL型の国産型) 2型 FFL型の国産化した型 3型 1号3型の初速増大型 零戦52型 4型 1号4型の初速増大型 52型甲以後 5型 2号4型の初速改良型 烈風 でその性能なんですが、威力としてはさすがに20mmだけあって強力でしたが、 対抗するアメリカの戦闘機の12.7ミリ機銃は、弾道と発射速度、携行弾数の点で日本の それに勝っていたようですね。多銃主義の米機 これも物量というべきか・・・
今回は零戦の好敵手 米海軍編です。 対ブルースターF2Aバッファロー 緒戦のころ、アメリカ及びイギリス両軍によって基地戦闘機として使用され、 F4Fよりも古くかつ性能が劣り、零戦にはよい餌食であった模様。 対グラマンF4Fワイルドキャット 艦上機らしい性格という点では零戦と似ており、本機のほうが馬力が少し大きく 急降下速度が同程度という以外、いかなる高度でもあらゆる性能で零戦が優って いた。同性格の戦闘機であることから、緒戦のころ格闘戦がよく行なわれ、零戦 の特徴が100%発揮された相手だった。 しかしながらガダルカナル争奪戦では、アメリカの設営力、補給力と絶対多数の本機の 働きが、アメリカ側に勝利をもたらした中核的戦力だといえよう。 対チャンスヴォートF4Uコルセア 単発戦闘機で零戦の好敵手として初見参したのが、海軍のF4U戦闘機でだった。 本機は高速を狙ったため着艦性能と視界が悪く、母艦上では使用できなかったが 主反攻は陸上基地を使用できるガダルカナル島から始まったので、日本軍が撤退した 昭和18年2月からソロモン戦線に投入された。 本機は最初の2000馬力級エンジンを装備し、零戦よりも相当優速で特に急降下速度が 大きく、数が少ない間は零戦で何とかなったが数が増し、戦法が研究されてから はその特有の性能がものをいい、うるさい相手となった。 対グラマンF6Fヘルキャット F4Uと同じく零戦の二倍にあまる馬力の「ダブル・ワスプ」を装備し、低翼面荷重を 玉条とした設計方針によって、主翼は31平方メートルという大面積となり、大面積は重量 増加を呼び起こすという循環の結果、自重は4180キロ(烈風の約25%増し)、総重量は 5800キロに達する大型戦闘機となった。 しかし馬力荷重、翼面馬力が零戦より有利で、急降下速度、火力、防弾で零戦に 優り、航続力、旋回性能で劣っていた。特に垂直面内の空戦では零戦について ゆけず、零戦が得意とするひねり上げるような旋回を行なった場合、四分の一周 も追従できなかった。零戦に追尾されたら急降下によって離脱するしか方法が なかった。 上昇力は高度3000メートルまでは零戦が優り、5000メートル以上では本機が優っていた。 まともに零戦と戦ってよい勝負をしたのは、アメリカ機中本機だけであった。
前回に続き零戦の好敵手 米陸軍編です。 対ベルP39エアコブラ、カーチスP40ウォーホーク どちらも陸軍航空隊の戦闘機で、特にP40ははじめのころ基地に多数配備され よく零戦の相手になった。どちらも馬力の割り合いに重く零戦よりも急降下速度 が大きく最高水平速度は同等、その他の性能は全て劣っていた。たとえ得意の 急降下速度を利用する一撃離脱主義で立ち向ってきても、そう手ごわい相手では なかった。 対ロッキードP38ライトニング この双発双胴の戦闘機は、翼面積の割りにエエンジンの馬力が大きく、かつ排気 タービン加給器を備えた高空性能はすばらしく、急降下速度も大であった。その反面 旋回性能と低速での操縦性の悪いのが特徴であった。 初めの頃はしばしば零戦に対して空戦をいどんできたが、零戦は常に優位をしめ これを撃墜した。後にアメリカが零戦の高々度における性能不足と、急降下速度の 小さいのを見抜いて、本機に対し常に高空性能と急降下速度を活用する、奇襲的 戦法をとられ、それ以降は好機に恵まれない限り、捕捉できなくなった。 対大型機 大型機としてはアメリカ陸空軍の4発爆撃機ボーイングB17とコンソリデーデットB24があった。 零戦が最初に手こずったのはB17で、近代的なセルフ・シーリングタンクと死角の少ない 防御銃火、4発機ならではの大搭載量、大航続力を誇っていた。 B24はB17より防弾で劣っていたが、航続距離は1〜2割優っていた。 この機種を墜としにくいのは、弾が当たっても火災を起こしにくい防弾タンクのほか 次の理由により弾丸が当たらなかったことも見逃せない。 1.すなわち死角のほとんど無い防御銃火のため、我が戦闘機が近接しにくいこと 2.機体が大型であるため距離を誤判断しがちなこと 3.パイロットの心理的な作用がそれであった。 勿論全然墜ちないというのではなく、我が老練な戦闘機パイロットが狭い敵機の死角 をぬい、充分近接し搭乗員とくに操縦者を狙うか、タンクに多数の弾丸を撃ち込むか 叉は多数の戦闘機が敵機を囲んで満身創夷にすることで、それを可能とした。 欧州戦線も含めて「空の要塞」B17がはじめて敵弾に撃ち落とされたのは、太平洋 戦争の開戦初頭、南台湾の基地から長駆フィリピンのルソンン島を空襲した、台南航空隊 零戦隊の坂井三郎小隊によってであった。
日本における いや世界における攻撃用戦闘機の代表選手が「零戦」でしょう。 パールハーバーの奇襲では、零戦の制空隊が完全に戦場を制圧、同時に雷撃隊、爆撃隊 が突入し米太平洋艦隊の主力を撃滅し、さらに零戦隊は銃撃で敵の航空戦力を 地上で破壊しました。 しかし大戦初期においては無敵だった彼らも、連合軍側に新鋭機が登場すると これら万能選手的な戦闘機「零戦」は、苦難の時代になっていきました。 兵器というものは、常に敵よりも優秀なもので必要な量を満たし、さらにその 補給ができなければなりません。 特に飛行機というものは、工業力の総合的製品であるから、機体、発動機、火器 等のトータルバランスがとれていなければ、戦闘機としては劣悪なものとなります。 開戦時は世界最強を誇った零戦でしたが、いかに改良をかさねてみたところで 高度10000m以上を飛ぶ「超空の要塞」B29に対する迎撃機として、使えなかったこと はその設計思想を見ても、当然でしょう。 つまり零戦の衰退(というか限界)が、そのB29による日本本土爆撃を許し、優秀な 飛行機を大量に生産するという戦い=技術と生産力の戦いに敗れた事になります。 零戦はそういう意味で「日本の運命を背負った戦闘機であった」 という言葉で、 このシリーズの最終回を結びます。御静聴ありがとうございました。
また 読者のみなさまの ご感想をいただければ幸いです
ご感想のメールはJU87氏に転送いたします